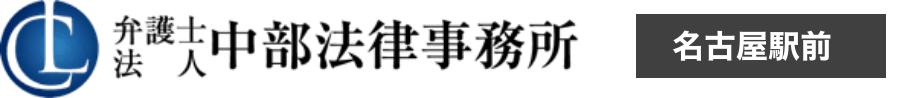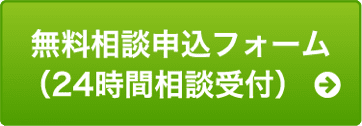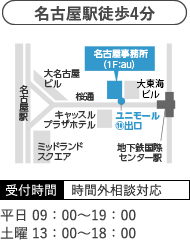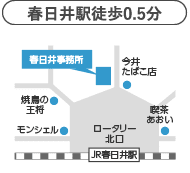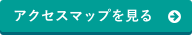今回は,簡単・分かりやすい民法改正解説シリーズの第16弾です。
今回は,前回の続き、大きく改正されることとなった「債権譲渡」の第2回です。
前回は、基本である債権の譲渡性については改正がなく、ただし、譲渡を制限(禁止を含む)特約について、用語と、譲渡制限特約に反して債権譲渡がなされた場合の効果に関する改正が行われることを解説・説明しました。
(前回のコラムはこちら:簡単・分かりやすい民法改正解説~シリーズ15 債権譲渡①改正の概観・譲渡制限特約~)
今回は、譲渡制限特約に反して債権譲渡がなされた場合に、現行では原則として債権譲渡が無効になるとされているのに対し、改正案では、原則として有効とされると、効果が転換されることに伴って生じる改正点について、詳しく見ていきます。
譲渡制限特約改正に関連する問題→改正案466条4項から466条の5まで
前回及び上述のとおり、譲渡制限特約に反して債権譲渡がなされた場合に、現行では原則として債権譲渡が無効(絶対的効力説)なのに対し、改正案では原則として有効とされる(相対的効力説)という、転換に伴って、いくつか対応が必要な問題が出てきます。
改正案466条4項から466条の5までは、そのために設けられた規定だと整理すると、わかりやすいと思います。
デッドロック問題への対応(改正案466条4項)
債務者は、譲渡制限特約について悪意・重過失の譲受人からの請求を拒絶することができますが、拒絶しないで譲受人を債権者と認めて支払ってもよいのです(明文規定は設けられませんでしたが、従来の判例でも認められているところで、当然と解されています。)。
しかし、債務者が、譲渡人にも譲受人にも任意に弁済しようとせず、譲渡人も回収しようとしない場合、譲受人はどうすればいいのでしょうか。
相対的効力説のもとでは、譲渡人にとって債権回収のインセンティブが低くなり、このようなことが生じやすくなると懸念されています。
一方で、譲受人には履行の強制ができないため、膠着状態(デッドロック)に陥りかねません。
そこで、改正案466条4項は、債務不履行の場合に、悪意・重過失の譲受人から債務者に対して、譲渡人への履行を催告できることとしました。
催告の期間内に譲渡人に対する履行がなければ、3項の適用がなくなります。すなわち、その後は譲受人でも自ら債権回収できるようになるのです。
債権者不確知の供託ができなくなる問題への対応(改正案466条の2)
現行民法では、譲渡制限特約付き債権が譲渡された場合、譲受人が善意か悪意かによって債務者の取るべき対応は全く異なり、債務者にとっては、債権譲渡が有効か否か、よくわかりません。
そこで、この場合、「債権者を確知することができない」(現行民法494条)という理由で供託をして、債務を免れることが可能です。
しかし、相対的効力説のもとでは、譲渡制限特約に反した債権譲渡も有効であり、債権者は譲受人であることが確実なため、債権者不確知とはいえなくなります。
これを受けて、改正案466条の2は、新たな供託要件となる規定を設けました。
すなわち、譲渡制限特約付き債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人が善意か悪意かにかかわらず、供託することができます。供託された金銭を還付請求できるのは、もちろん譲受人だけです(同条3項)。
譲渡人破産の場合に不合理が生ずる問題への対応(改正案466条の3)
破産手続開始決定があると、管財人が破産者の財産を管理し、回収すべきものは回収してすべて金銭に換価したうえで、配当手続により債権者に公平に分配します。
相対的効力説のもとでは、譲渡制限特約付き債権の譲渡人が破産し、管財人が債権を回収したとすると、譲受人は管財人に対してその回収額を不当利得として請求でき、この場合の譲受人の債権は財団債権といって、配当を待たずに優先的に弁済してもらえることになると考えられます。これに対し、絶対的効力説ならば譲受人の債権は破産債権として配当を受けられるだけとなります。
管財人にとっては、回収しても結局引き渡すだけとなるので、債権回収のインセンティブが働かなくなるのではないかと懸念されています。
また、破産者の財産が財団債権にも満たなければ、財団債権でも全額の弁済を受けられない可能性が出てきますが、これではせっかく債権譲渡を受けた譲受人にとって努力した甲斐がなくなります。
債務者の立場を考えても、元の債権者が破産して管財人に支払わなければならなくなったことで弁済の相手を固定する利益は半減されています。
そこで、改正案466条の3は、このような場合に譲受人から債務者に供託をするよう請求できることにしました。供託金の還付請求をするのは譲受人であり、これによって、譲受人は破産手続外での債権回収ができることになります(倒産隔離)。
譲受人の債権者が差押えできるようになることに伴う問題への対応(改正案466条の4)
債権は差し押さえることができます。
たとえば、譲渡制限特約付き債権の債権者Aに貸付をしているBがいて、AがBへの返済を遅滞したとします。
Bは、Aの財産である債権を差し押さえて自分の貸付債権の回収を図ることができます。
差し押さえられた債権は裁判所の転付命令によってBに移転し、Bは直接Aの債務者であるCから取り立てることができます。
このとき、たとえBが悪意・重過失であっても、Cは譲渡制限特約を主張してBへの履行を拒むことはできません。
AからBへ債権譲渡があった場合と似たシチュエーションですが、公的な手続きである差押えに関しては、私人の合意で差押禁止債権を作り出すことはできないという理由で判例がこのような結論を採用していました。
今回の改正で、このルールが明文化されました(改正案466条の4第1項)。
ところで、譲渡制限特約付債権の債権者Aが、Bに債権譲渡をした後に、Bの債権者であるDがBに移転した債権を差し押さえて来たらどうなるでしょうか。
改正案では、債権譲渡制限特約に反した債権譲渡も原則有効(改正案466条第2項、相対的効力説)、Bが悪意・重過失であっても有効(改正案同条第3項)に債権を取得できるので、Dの差押えも有効になります。
しかし、改正案466条第3項で、Bが悪意・重過失の場合、債務者Cへの履行を拒絶することが認められています。このケースで、債務者CがDに対しては履行を拒めないとしたら、DはBが有していた以上の権利を取得することになって不当と考えられます。
そこで、改正案466条の4第2項では、このような場合にCはBに対するのと同様にDへの履行を拒めるというルールが設けられました。
預貯金債権特有の問題への対応(改正案466条の5)
預貯金債権は一般的に譲渡禁止特約が付けられています。
そして、このことは誰でも知っている公知の事実と考えられ、知らないことは重過失と判断する判例もあります。
そうだとすれば、相対的効力説のもとでも金融機関は常に譲受人への払戻しを拒絶することができるため、問題なさそうに思えます。
しかし、預貯金債権には頻繁に額が増減するという特徴があり、ある時点で譲渡があっても、その後に増額した部分は譲渡の対象ではないと考えなければなりません。
譲渡後に元の口座名義人の債権者が預貯金債権を差し押さえた場合、従来は譲渡が無効という前提のもと、全額について差押えは有効として対応していたのが、相対的効力説では譲渡の対象となっていない一部のみについて差押えが有効ということになり、それはどの範囲なのか金融機関がいちいち判断しなければなりません。大量の預貯金債権を扱う金融機関の業務にとってこのことは著しい支障となり、ひいては一般の利用者にも不利益が及ぶだろうと思われます。
そこで、改正案466条の5において、預貯金債権について、相対的効力説の例外を認める特則を設けました。
すなわち、同条1項において、債務者(銀行などの金融機関側)が、譲渡制限の意思表示を、悪意・重過失の譲受人に「対抗することができる」と規定し、預貯金の払い戻しを拒めるということです。
なお、対抗できるとの表現は、現行民法466条2項の表現にならったもので、絶対的無効を意図したものだそうです。
もっとも、口座名義人の債権者による預貯金債権の差押えは従来どおり有効ですから、改正案466条の5第2項でこのことを明記しています。
終わりに
今回は、譲渡制限特約に反して債権譲渡がなされた場合の債権譲渡について、原則無効とする現行の民法に対し、改正によって原則有効と転換することに伴って生じる問題への対応について、解説・説明しました。
次回は、現行民法には規定のない、将来の債権に関する譲渡について、詳しく見ていきたいと思います。